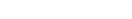遊女は古代から「あそびめ」とも「あるきめ」「流れの君たち」などともいわれてきた。
「遊び」は「神遊び」に通じる神聖な行為であり、巫女の専業でもあった。平安末期に後白河法皇が遊女たちから聞き取った歌謡を記録した『梁塵秘抄』に、「遊びをせんとや生まれけむ、たわぶれせんとや生まれけん」とあるように、現世の生を讃える、歌舞音曲に携わる女たちがいたのである。
『義経千本桜』に登場する静御前も、『吾妻鏡』によれば白拍子という遊芸の徒であったという。遊女は古くは江口や津などの港町にいて、能の『江口』で西行が出会った遊女は、実は普賢菩薩の化身であったとされる。平景清が馴れそめた阿古屋は京の清水の五条坂の遊君だったし、曽我五郎が雨夜に傘をさして会いに通った恋人も、大磯の廓の遊女であった。このような遊女は勇者の守護神として神格化され、敬慕と畏怖の対象ともなった。
港や宿場、高名な社寺の門前町など、大勢の人が行き交うところには遊里があり、遊女が酒席にはべる社交場として、また歓楽の巷として繁盛した。
江戸幕府は、こうした遊女を置く妓楼を特定の地域に集めて、一般の市街地から隔離することを推進した。そして城郭のように堀割や塀などで囲ったので、廓(くるわ)とか遊郭(ゆうかく)とも呼ばれる。江戸なら吉原、京都では島原、大坂では新町が、幕府公許の遊郭であり、当時の人々には一夜に千両の金を蕩尽する、豪奢な「異界」であった。しかしまた、この三カ所以外にも、遊里は各地に数多くあった。
遊郭で起こるさまざまの恋模様や達引は、男と女の悲喜こもごものドラマであり、歌舞伎や浄瑠璃のかっこうの題材となっている。(小宮暁子/浅原恒男)